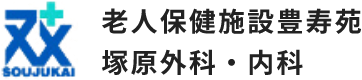Poison & Medicine ブログ 毒と薬
カテゴリー: 歴史と文化

「お馬祭り」にも少子化の影響が‥‥
令和7年10月12日(日)。 小牧神明社の秋祭り「南……
2025.10.22

語り継ぐ「小牧と太平洋戦争」⑦
空襲で妹二人を失ったわたしの母 わたしの祖父・塚原嘉……
2025.8.15

語り継ぐ「小牧と太平洋戦争」⑥
米軍に救助され捕虜として終戦を迎える 突然、右腕にチ……
2025.8.15

語り継ぐ「小牧と太平洋戦争」⑤
重巡洋艦「鈴谷」の壮絶な最期 突如、耳をつんざく大爆……
2025.8.15

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』④
利用者で最後の出征経験者 今日は80年の節目を迎えた……
2025.8.15

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』③
今日8月9日は長崎に原爆が投下された日です。 第3章……
2025.8.9

語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』②
第2章は、わずか5年半という短期間、東春日井郡篠岡村字下末……
2025.7.25
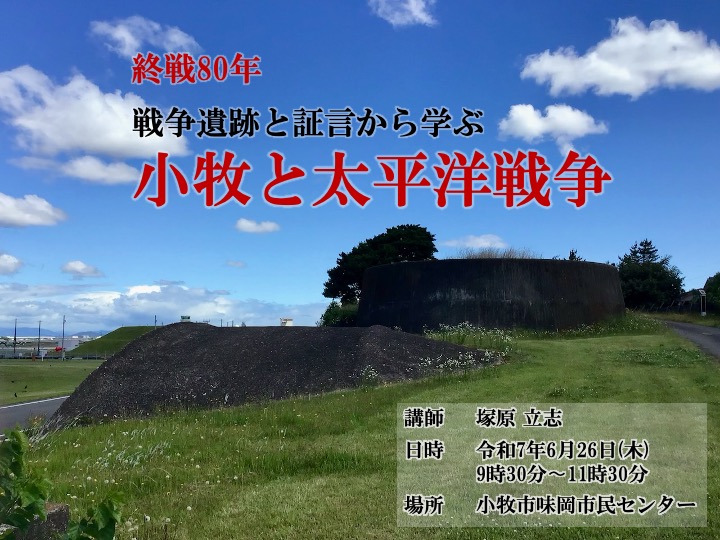
語り継ぐ『小牧と太平洋戦争』①
6月26日、木曜日。小牧市教育委員会からの依頼でゆうゆう学……
2025.7.9

昭和30年代の武者飾り〜人形職人のこだわり
ゴールデンウィーク真っ只中。 ご利用者に季節感を味わ……
2025.5.2

花祭りと庭園の桜たち
4月8日、春晴れ。花祭り。室内では花御堂(みどう)……
2025.4.9