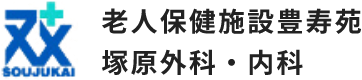Poison & Medicine ブログ 毒と薬
2025.5.2
豊寿苑
歴史と文化
イベント
昭和30年代の武者飾り〜人形職人のこだわり
ゴールデンウィーク真っ只中。
ご利用者に季節感を味わっていただければと、「端午の節句」は屋外に鯉のぼりを上げ、1階和室に五月人形を飾っています。


(左)左下から「飾り馬」「鍾馗(しょうき)」、左上から「祝い兜(かぶと)」、「連獅子」
(中央)「鎧(よろい)武者飾り」
(右)左下から「六方弁慶」「牛若」「暫(しばらく)」、左上から「橋弁慶」「毛利元就 兜」「金太郎」、背景「鍾馗幟(しょうきのぼり)」

昭和35年(1960)頃。
上段は大鎧(おおよろい)と武者人形。
背景に、豊臣秀吉と加藤清正の主従、丸に沢瀉(おもだか)の家紋を描いた旗標(はたじるし)、秀吉の瓢箪馬標(ひょうたんうまじるし)などが見える。
下段は陣笠、陣太鼓、軍扇(鉄扇)、采配、かがり火など。
贅(ぜい)をこらし、人形職人の技術の高さが凝縮された名品です。

平安・鎌倉時代の騎馬武者の大鎧をモデルにしています。高さは「鍬形」を含むと約80cm。
「面頬(めんぼお)」「籠手(こて)」「佩楯(はいだて)」「脛当(すねあて)」は安土・桃山時代以降なので時代考証としてはおかしいのですが、そこは工芸品、お許しください。
次に甲冑解説。

材料は布と糸と紙と金属。プラスティックは使われていません。面頬もブリキ製です。
ミニチュアながら、あまりに精巧に作られているのに感心しました。

ブリキ製の鉢に文様が施された金属片を被せて鉢の裏側から留めています。
だから、65年経ってもまったくはがれていません。前立の竜頭(りゅうず)は真鍮です。

甲冑の胴・袖・草摺は、札(さね)と呼ばれる高さ5〜7センチの縦長のチップの穴に、威毛(おどしげ)と呼ばれる鮮やかな紐を通し、これらを縦横に組んで作られています。

ここでは本小札(ほんこざね)一つ一つが横に並んでいるように似せた、切付小札(きりつけこざね)といわれるブリキの一枚ものが使われています。

本物の大鎧は、膨大な数の本小札を使って一つ一つ組んでいくのですから、モデルにしたと思われる春日大社の赤糸威大鎧(あかいとおどしおおよろい)が国宝に指定されているのも理解できます。

大鎧では、草摺は鞍に跨がった時に大腿部を四方の箱のように囲んだ形の「四間草摺」ですが、こちらは六つの草摺からなる「六間草摺」です。
馬にまたがった状態で佩楯があったら邪魔でしょうがないですね。あくまで工芸品ですから。

中世まで馬上の上級武士が戦場に履いていたのは貫(つらぬき)と呼ばれる猪、鹿、熊など毛皮制の沓(くつ)でした。
しかし、日本の戦場ではむしろ、素足の草鞋(わらじ)か、足半(あしなか)と呼ばれる踵部分のない半円形の草履(ぞうり)を履くのが一般的だったようです。

武者人形のキリリ引き締まった容姿は、武士というより昭和陸軍の将官・将校の理想型を引き継いでいるように思えます。
わたしの目には「威厳がある」というより「無理している」ように映りました。まるでわたしだ。