手拍子こそ最高のパーカション!
1月17日(日)、ご入所者とその家族の方々をお招きして医療法人双寿会「新年会」を開催しました。
第一部の食事会のあと、第二部では地元の「森民謡会」のみなさんの公演をご覧いただきました。
ライヴは、演者(パフォーマー)と聴衆(オーディエンス)との協同作業です。パフォーマーがノレばオーディエンスはノリ、ノッたオーディエンスの反応にパフォーマーはますますノッて、いつしかパフォーマーと聴衆との「交響」(シンフォニー)、ダンス音楽的にいえば「グルーヴ」が生まれるわけです。
オーディエンスがパフォーマーをノせるもっとも有効な手だては手拍子(ハンドクラップ)です。ところが当施設のご利用者には、脳こうそくなどの後遺症で手拍子がままならないひとたちも多くおられます。そこでわたしは、ひと一倍大きな音で手拍子(ハンドクラップ)を鳴らすテクニックを身に付けました。
手のひらに空気を軽くタメるようにして左右の手を交差に瞬時に叩きつけると「パッーン」という見事な破裂音が出ます。 会場に使う豊寿苑の1階食堂は、ステージあたりが吹き抜け構造になっているので、音響が思いのほかよくて、「森民謡会」のみなさんの演唱に合わせてハンドクラップしているうちに、いつしかトランス状態に入っていました。
ハンドクラップの反復されるリズムは、おそらく心臓の鼓動とシンクロして、脳波でいえアルファ波、瞑想状態を生み出します。 こ
の状態にあるとき、先人は「神」の隣在を実感したのでしょう。神社で柏手を打つと「パーン」という音が森の奥深くに沁み込んで、ときにこだまして荘厳ですらあるのを思い起こしてください。
そういえば、パキスタンのカッワリーは、声とハンドクラップとのインタラクションをとおしてアラーと一体化するトランス系の音楽です。また、モロッコやエチオピアなど北アフリカのサハラ砂漠周辺の乾燥した地域の音楽でも同様と感じます。
彼の地でハンドクラップは「ユーユー」とよばれる独特の喉笛とともに、人口密度の低い、乾いた大地でのコミュニケーション手段としても欠かせないものでした。
なんにせよハンドクラップというのは、もっともプリミティブにして、もっともクールな打楽器だと再認識しました。 介護スタッフの気のない手拍子を見るにつけ「どうせならそれをマテリアル(素材)に自分勝手にグルーヴすればいいじゃん」と感じるのですが、なんてかれらは生真面目というか不器用なんでしょう。
「常識」は「常識」ではない?
デイケア送迎のドライバーをしている50代の男性職員がわたしにこんなグチをもらしました。
20代前半の新人の男性介護スタッフが自分を目の前にしながら、あいさつしなかったので注意した。かれは一瞬顔をこわばらせて、ひとことも発することもなく目を反らしてしまった。それからも、かれはずっと自分を無視し続けている。そんな態度に我慢がならないと。
わたしはこう答えました。
あなたは、かれが謝罪するにせよ反発するにせよ、自分とおなじ土俵でシロクロを付けることを暗に期待していたのだろう。
が、かれは土俵に上がってこなかった。なぜなら、かれの頭の中にはあなたとのトラブルを避けたいということしかないのだから。それでかれはあなたを「無視」することで「自分の世界にあなたがいない」ことにしてしまった。ケータイでいえば「非通知設定」、電子メールでいえば「フィルタリング設定」のようなものであると。
思えば、わたしが昨年発表した『ヤンキー介護論』は、いわゆる「社会常識」「職業倫理」にあわせてかれらを「矯正」しようとしてもムリであり、それよりもかれらの価値観をそれとして受け入れズラしていくことに力を注ぐべきだというものです。
「かれらのレベルが低い」とするのは「社会常識」なるものを内面化している自分の価値観と照らし合わせてのことでしかありません。世代論を語りたくはありませんが「かれらとは次元がちがう」と開き直った方が自分の身を守るうえでもよほど気が楽です。
双寿会には医師やわたしのような高学歴の者もいれば、中卒の介護職員もいて、それらのひとたちが近い距離で接する職場環境にあります。
かれらと接していて、合理的にはどうみても自分で自分の首をしめることになる判断をかれらが平気でとることによくとまどいます。それはときに「経営者」の立場からすればありがたかったりするのですが、「価値中立的」にみると賛同できません。ついでにもうひとつマックス・ウェーバーの用語を用いるなら、かれらの行為は「目的合理的行為」ではなく「感情的行為」なのです。
論理でかれらをねじ伏せるのは簡単です。でも、そのときかれらは「納得」したのではなく「屈服」させられたにすぎません。こうしてもの言わぬかれらの心の奥にルサンチマン(怨念)がふり積もります。わたしはそれらが堰を切って噴出することのほうがこわい。
だからわたしは、かれらの「島宇宙」をむやみに「開発」するのではなく、「保全」しながら社会化させていくのが最善の策と考えます。
2010.01.27 | 介護社会論
10月1日朝日新聞朝刊の「私の視点」に、コラムが載りました。
ヤンキーが介護を救う
ショッピングセンター、イオンが近くにある名古屋近郊の地方都市で、私が介護老人保健施設の運営に関わるようになったのは95年のこと。バブル崩壊の後遺症が残る就職難の時代で、阪神淡路大震災を機に高まった自分探しとしてのボランティア・ブームと、新設されて日の浅かった「介護福祉士」という国家資格への期待とが結びついて、介護職の募集に対して多くの若者たちが殺到した。
大多数は女性で、総じて向上心が高く「手に職」志向が強かった。消費社会研究家の三浦展氏が「かまやつ女系」と呼んだタイプに近いが、将来設計がしっかりしていた点がちがっていた。なかには高学歴でありながら、客室乗務員や教員など、将来、他職種に就くためのステップとして介護の仕事を経験した究極の「手に職系」もいた。
ところが、介護保険制度の導入から5年が経ち、経済が回復基調に入った05年頃から、「かまやつ女系」の応募がめっきり少なくなった。この頃になると、介護は「重労働」「低賃金」「将来性なし」という「負け組」の仕事として、世間的には負のイメージで見られるようになっていた。さらに、07年の「コムスン問題」が逆風になって、介護の現場は深刻な人員不足にみまわれた。
そんな苦境にあえぐ現場を、介護の専門学校などを卒業したスタッフ(総じて「純情まじめ系」)とともに支えてくれているのが、50代以上の女性と、「ヤンキー系」と呼ばれている男女たちである。
ヤンキー系とは、社会学者の難波功士氏が著した『ヤンキー進化論』(光文社新書)によると、 階層的・文化資本的にロウアー、早熟・早婚、旧来型の男女性役割(男性が女性に対してセクシャルであり家庭的であることを求める)、地元(でまったり)志向、を特徴としている。
私は、施設で働く介護職員の過半数以上がこの本に書かれているヤンキーの価値観や行動特性に当てはまることに驚いた。時流に反して、介護職員の喫煙率が高くなってきたのもヤンキー化現象と解釈すれば合点がいく。施設裏手に設けた屋外喫煙場所の側を通りかかると、2、3名が「ウンコずわり」になって煙草をふかしながら「おつかれさま~」と気のないあいさつをするのも、かれらなりの上司への敬意だったことがわかった。
ところで、最近、介護従事者の質を高めようと、介護の知識や技術の習得だけではなく、「人間の尊厳と自立」「人間関係とコミュニケーション」といった介護理念の教育の必要がいわれている。まさにその通りだが、かれらにそれを教えようと思ったら義務教育のレベルからやり直さなければならないだろう。
また、「協調性」「積極性」「規律性」「責任性」などからなるこれまでの人事考課制度もかれらの前では無力である。基準に則って評価しても、多くの面で「標準」以下と判定され、収入面での不利が結果的にかれらの離職を促すことになってしまうからである。
ヤンキーへの依存が専門職としての介護の質の低下をもたらしたことは残念ながら事実だ。しかし、これからの介護現場を下支えしていくのはまちがいなくかれらである。ならば、ヤンキーの負の側面ばかりをいうのではなく、ポジティブな面を引き出すことを考えたほうが建設的ではないか。
ヤンキーには「言葉や態度はすこし乱暴だけど気持ちはピュアで根はいい子」というイメージがある。当施設のスタッフにかんする限り、これは当たっている。かれらが介護の仕事を選んだのは、多くの場合、学校や社会の中心から外れ、自分の居場所が見つけられずにいたところに、お年寄りがかれらを必要とし存在証明を与えてくれたからだ。
ただし、社会学者の阿部真大氏が『働きすぎる若者たち』(NHK出版生活人新書)で指摘したように、このような「やりがい」を動機づけとする感情労働はバーンアウトの危険をつねに孕んでいる。
そこで注目したいのが、かれらの地元志向/祭り好きである。つい先日、私の施設でも地域社会と一丸となっての盛大な夏祭りが催された。多忙な業務の合間をぬっての作業だったにもかかわらず、スタッフの夏祭りに賭ける情熱と熱狂は並大抵ではなかった。
伝統的な地域の祭りではなく、自分たちで創造した夏祭りの非日常的な共同性(コムニタス)に身を投じることが、かれらの日常労働のストレス緩和につながったことはたしかだろう。あるスタッフは「夏祭りがあるからここに勤めている」と言っていたが、あながち誇張ではないと思っている。
介護の未来に役立つにちがいないもう一つのヤンキー特性は、いまやヤンキー文化論の第一人者と目されている故ナンシー関氏が99年に発表したコラムに示されている。ナンシーは、当時人気絶頂だったヴォーカル・ユニットSPEEDの解散会見で、中学生だったメンバーの島袋寛子が口にした「故郷(オキナワ)に帰ってお店をやりたい」という発言をとらえ、そこに「お店気質」というヤンキーの世界観を見て取った。美容師、菓子職人、それからいわゆる「お水系」の人たちなどにありがちな、この「お店気質」を介護で働く人たちにも適用できないものか?
介護職員の高い離職率は、低賃金など処遇への不満や人間関係のストレスなどが主要因にあげられるが、その背景には将来が見えないことへの不安がある。これを重く見た厚労省は介護職員の処遇改善計画の中に、賃金の上乗せとともに、「キャリア・パス」といって、教育や研修などの人材育成環境を充実させ、将来において介護職員が能力や地位を向上させていけるようなライフコースの整備を施設や事業所に求めようとしている。
しかし、これは一部のエリートたちが自分たちの価値観にもとづいて「上から目線」で考え、押しつける「介護職のあるべき将来設計」でしかない気がする。述べてきたように、介護で働く人たちの大多数は専門職としてのスキルアップよりも、無理しない程度に「ジモト」でまったりと暮らしていければいいと感じていると思うからだ。
だから、私は、ヤンキー系介護職員が将来において「ジモト」で介護の「お店」が持てるような流れがあってもいいと思う。
現在、厚労省は、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活し続けられるように、地域密着型の小規模のサービス拠点の整備を進めている。ところが、これら小規模型の施設や事業所を起ち上げるには、一定以上の法令読解力と、ぼう大な手間と、資金力と、ネットワークとが必要なため、一介の介護職が個人でできる範囲を超えてしまっている。その結果、それらはすでに施設や事業所を有する社会福祉法人や企業などが運営するところとなり、「キャリア・アップ」した介護職員は「雇われ管理職」としてそこを任されて、それなりの給与とひきかえに多くのリスクと責任とを負わされることになる。「キャリア・パス」の行き着く先はせいぜいこんなものではなかろうか?
そこで私は行政に求めたい。介護職員が一定の経験と実績を積めば、フランチャイズではなく、「のれん分け」というかたちで勤務先から完全独立でき、個人事業主として介護サービス事業所などを開業できる体制を整備してもらいたい。市町村はかれらに対して、当初は必要書類の作成から、資金の調達、経営のノウハウまで、手取り足取り面倒を見ていってあげる必要があるだろう。また、開業後も、実地指導や監査によってサービス内容を書面のみでチェックするだけではなくて、経営が安定するまで一定の優遇措置やアドバイスを継続しておこなうべきである。
このように、こよなく地元を愛する地元志向のヤンキーたちこそ、衰退する地域コミュニティの救世主であり、厚労省がめざす地域密着型の介護・福祉空間を支えていける適任者といえる。そのためには、介護の専門性を高めて介護労働の社会的地位の向上を図ることよりも、肉体労働(マニュアル・ワーク)として下位の階層がする仕事と社会的に位置づけられようが、介護の仕事そのものに誇りが持てて、がんばれば自分のお店が持てるかもしれないという夢のあるものに導いていくべきと考える。そして、地元で安定した収入が得られれば、子ども好きの多いヤンキーたちのこと、きっと少子化対策にも貢献してくれるにちがいない。
2009.12.24 | 介護社会論







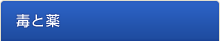
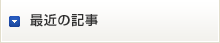

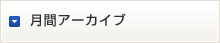


![塚原外科・内科[TEL:0568-77-3175/FAX:0568-76-8173]](http://www.soujukai.or.jp/wp-content/themes/soujukai/images/common/banner_info_tuka.png)
![老人保健施設 豊寿苑[TEL:0568-71-8281/FAX:0568-76-1498]](http://www.soujukai.or.jp/wp-content/themes/soujukai/images/common/banner_info_hou.png)
![居宅介護支援事業所 ケアサポート 双寿会[TEL:0568-73-6543/FAX:0568-73-6554]](http://www.soujukai.or.jp/wp-content/themes/soujukai/images/common/banner_info_sou.png)