もちつきリハビリ? 今年最後のイベント「もちつき大会」

文字どおり「昔取った杵柄」とはこのこと
年も押し迫った平成26年12月26日。
豊寿苑、今年最後のイベント「もちつき大会」をおこないました。
スタッフの中で臼と杵で餅を搗いた経験がある者はほとんどいません。
厨房から熱々の餅米が蒸し上がってきたら、これをすかさず石臼に投入します。
餅を搗く前に、餅米を杵で臼に押しつけしっかりとこねまわします。これは腰を入れないとできない作業なので、もっぱら私とベテランの元運転手がおこないました(地味!)

餅米を杵で地味にすりつぶしているオジさん75才とオレ53才(スポーツクラブ仲間)
そのあと、いよいよ見せ場の餅搗きです。
返しの役は、数少ない餅搗き経験のある女性スタッフが担当。ところが、出てくる男性スタッフはどいつもこいつもへっぴり腰でフニャフニャ。

餅の弾力に跳ね返されるぐらいソフトな男子の餅つき
見るに見かねて、餅搗き役に女性スタッフが名乗りを上げました。これをきっかけに、次々と女性スタッフたちが餅搗きに参戦。
多少腰が引けていますが、男性スタッフたちに比べれば、勢いと元気さがあってサマになっていました。応援していたお年寄りのみなさんも大盛り上がり。その間も、男子たちは「ヨイショ 」の掛け声(ならぬ脱力的なつぶやき)で場を涼しくしてくれました。

元気さと無茶ぶりで場を盛り上げた女子たちと、クールに「ヨイショ」とつぶやく男子
「はじける女子」と「草食系男子」。
豊寿苑の女性上位の縮図がそのまま再現されました。
搗き上がった餅は餅取り粉をまぶした板の上に運ばれます。これを女性スタッフたちが顔を粉まみれにしながら和気あいあいと丸餅や花餅用の長餅に仕立ててくれました。

ノリノリで丸餅を作っている女子たち(とオジさん)
そして、三臼めで、スタッフのあまりに腰の引けた搗きっぷりに業を煮やした男性のご利用者が、臼のところに現れ杵を手に取ると、やにわに車イスからスクッと立ち上がったではありませんか!
施設ではずっと車イスで過ごしておられた方です。あわてたスタッフが介添えに付きましたが、その見事な搗きっぷりに周囲から喝采が沸き起こりました。

ふだんは車イスなのに? 勢いよく杵をふるう入所者の方
すると、我も我もと殿方連が名乗りを上げました。介添え役のスタッフはヒヤヒヤしながらもうれしくてたまらない様子でした。

どこにそんなパワーが残されていたのか?ビックリ
こうして搗き上がった餅は、残念ですが、お年寄りのみなさんに食べていただくわけには参りません。
その代わりに、伸ばして約1㎝幅のきしめん状にした紅白餅を小さくちぎって、木の枝に巻き付けて、飛騨高山の名物、花餅(もちばな)を作っていただきました。

ロビーに展示した花餅。花器は施設長の陶芸作品
ところで、きょうは平成26年12月30日。豊寿苑の仕事納めです。
今年1年、たいへんお世話になりました。
来年もよろしくお願い申し上げます。
よいお年をお迎えください。
2014.12.30 | 歳時記
認知症と音楽療法〜映画『パーソナル・ソング』を観て【3】
最後に、映画を観たスタッフたちに感想をまとめておきます。
みな感動していたようでした。なかには涙が止まらなくなったスタッフもいました。
同時に、自分たちの介護のあり方を反省するいい機会になったという意見も多く寄せられました。
いっぽうで、現場ならではのこんな意見もありました。
「本人にとってはたしかにいいことだと思いますが、これをおこなうには家族の理解と協力が不可欠です。ただ、そうまでして家族がそれを望むとは考えにくい気がします。本人以上に家族のニードをいかにかなえられるかが私たちの仕事になっていますから。」
「何年間も歩行器を使って移動していた人が、音楽を聴いて突然、自力でダンスを始めたシーンがありましたが、もし転倒して骨折でもしたらどうするのか、とヒヤヒヤしながら観ていました。」
映画で向精神薬が投与されているシーンがありましたが、豊寿苑では強い抗精神病薬こそ使っていませんが、睡眠薬が処方されることはあります。このことについて、認知症が重い人たちのフロアを担当しているスタッフはこういっていました。
「夜間に大声で騒ぎ立てたり、暴れまわったりする人がいると、他の入所者にまで影響が出てしまうのでやむをえないと思う。」
「それは理解できるが、こうしたことが繰り返されるうちに睡眠薬投与が常態化してしまう点についてどう思うか」の問いに、当人が黙ってしまったので別のスタッフが答えました。
「睡眠薬の服用は入所前からのケースが大半です。なかには自分から睡眠薬を要求される方もいるぐらいです。」
要するに「自分たちのせいじゃない」と。現場のスタッフも「当事者主権」について頭ではわかっていても、慢性的な人手不足にあえぐ介護の現場で日常業務を遂行していくとなると、個人の自由よりも安全を第一に考えざるをえなくなって、それが免罪符となって感覚が麻痺してしまうという悪循環です。
だからといって、彼らばかりを責めるのはお門違いで、私をはじめ、事業者、行政、家族などにも問題はあります。介護人材の不足といい、介護財源の問題といい、受け皿としての家族や地域共同体の弱体化といい、「本人のためにパーソナル・ソングを!」とどんなに思っても、それをサポートする側の足腰がこんなに不安定なのではとてもやりきれない、というのが現場の正直な声なのです。
(終)
※ 映画『パーソナル・ソング』は、2014年12月6日から全国の映画館で順次公開しています。(2014年12月18日現在)
※ 『パーソナル・ソング』についての私の映画評は、2014年12月20日発売予定の『ミュージック・マガジン』1月号に掲載されます。
2014.12.18 | 介護社会論
認知症と音楽療法〜映画『パーソナル・ソング』を観て【2】

ルイ・アームストロング
ところで、映画では、介護施設で認知症の高齢者をおとなしくさせるために向精神薬漬けにされている場面が映し出されます。薬の過剰投与は彼らの心の叫びを抑え込みますが解消されるわけではありません。そのうちに、彼らは心を閉ざして外の世界とのつながりを断ってしまいます。残念ながらこれは事実です。
それが、音楽の刺激によって記憶や感情がわき起こり、自分が取り戻せるというのですから、こんなにすばらしいことはないと思いました。
映画には、前出の曲のほかにも、たくさんの〝パーソナル・ソング〟が出てきます。わかっただけでもざっとこんな感じです。
サッチモことルイ・アームストロングの「聖者の行進 (When The Saints Go Marching In) 」、40年代に大人気だった白人3姉妹のジャズ・コーラス、アンドリュース・シスターズの「オー・ジョニー (Oh Johnny, Oh Johnny, Oh!) 」、フォー・シーズンズのリード・ヴォーカルだったフランキー・ヴァリの「君の瞳に恋してる (Can’t Take My Eyes Off You ) 」、キュートな4人組の黒人女性コーラス・グループ、シュレルズが歌って大ヒットしたキャロル・キングの名作「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロウ ‘Will You Love Me Tomorrow’ 」、ビーチ・ボーイズの「アイ・ゲット・アラウンド ‘I Get Round’ 」、ベン・E・キングの「スタンド・バイ・ミー ‘Stand By Me’ 」、ビートルズの「抱きしめたい ‘I Wanna Hold Your Hand’ 」「ヘイ・ジュード ‘Hey Jude’ 」「ブラックバード ‘Blackbird’ 」など。
ベートーベンのようなクラシックもありましたが、メインは40〜60年代のヒット曲です。
このラインナップをみて気づいたのは、75歳以上の高齢者の世代むけと思われる〝パーソナル・ソング〟がサッチモ、キャブ、アンドリュースなど、意外と少ないことです。

アンドリュース・シスターズ

シュレルズ
豊寿苑の利用者の平均年齢であてはめると、ビング・クロスビー、フランク・シナトラ、グレン・ミラー楽団あたりが出てきてもおかしくないはずですが、そうでないのは、コーエンの音楽療法が若年性アルツハイマーのようなもうすこし年齢の低い中高老年層を中心に試みられたからかもしれません。

左から、ボブ・ホープ、フランク・シナトラ、ビング・クロスビー
もう1点、不思議だったのは、60年代(とくに前半)の曲が目立っていたのとは対照的に、ナット・キング・コール、エルビス・プレスリー、ポール・アンカのような50年代を代表する歌手たちの曲もあまり使われていないことです。
躁うつ病のデニースはサルサで踊っていましたが、40年代末〜50年代に大流行したマンボもチャチャチャも出てきません。ラテン音楽ファンとしては納得のいかないところです(笑)。
このあたりはダン・コーエンの好みの問題なんでしょうね。
映画を見終わって、私もダンのように豊寿苑のご利用者を対象に〝パーソナル・ソング〟を試みたくなりました。音楽の知識ではダンより上だと思っていますから…。
ただ、むずかしいと思うのは、「音楽には興味がない」と答える人が意外と多いのではないかということです。たとえ音楽鑑賞が趣味でなくても、心に残っている音楽はだれにでもあるはずです。しかし、本人は無自覚でしょうから、その曲を探り当てるとなるとたいへんな手間と時間が必要になるのではないでしょうか?
そこでありがちだと思うのは、本人がもっとも充実していた時代に流行っていたヒット曲をいくつかピックアップして、それらを聴いてもらい、その中からもっとも反応がよかったものを〝パーソナル・ソング〟に選ぶという手法です。これだとヘタしたら、たんなる「年代別懐かしのメロディ」になってしまいます。
福祉や介護の世界は、真面目だけれども感性がベタでイケてない人たちが多いので、こうなってしまわないかと私は懸念しています。
たとえば、私が認知症になったとします。
生活歴や家族の話から、音楽マニアで、とくにアフリカやラテンなどのワールド・ミュージックが好きだったという情報から、セネガルのユッスー・ンドゥールが90年に発表した「SET」が私の〝パーソナル・ソング〟ということにされたとしたらちょっと複雑な心境です。
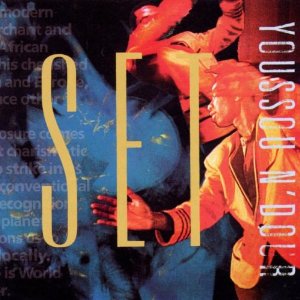
ユッスー・ンドゥールの90年発売の名作『SET』
たしかにユッスーの「SET」は大好きなので、私は相好を崩すのでしょうが、といって、これは私の〝パーソナル・ソング〟ではありません。
要するに、認知症の状態改善につながるのであれば、〝真実のパーソナル・ソング〟でなくても構わないという立場なのでしょうが、やっぱり納得できません。要するに、音楽にしろ、芸術全般はそれ自体が目的なのであって、手段ととらえた時点で、このような欺瞞は避けられない気がします。
私にはその人の〝パーソナル・ソング〟を勝手に決める権利はありません。だからこそ、〝パーソナル・ソング〟なのではありませんか?
13年11月のポール・マッカートニーの東京ドーム公演に行って確信しましたが、私のパーソナル・ソング〟はビートルズです。
認知症になったら、「ア・デイ・イン・ザ・ライフ (A Day In The Life)」か、「愛こそすべて (All You Need Is Love) 」を聞かせてください。
(続く)
2014.12.18 |  音楽とアート
音楽とアート
認知症と音楽療法〜映画『パーソナル・ソング』を観て【1】

映画『パーソナル・ソング』から
ある日、東京の知り合いの編集者から
「塚原さんにぴったりの映画が公開されるので映画評を書いていただけませんか?」
というメールをいただきました。
それは『パーソナル・ソング』という認知症と音楽について描いたアメリカのドキュメンタリー映画でした。
たまたま、『レナードの朝』の原作で知られるアメリカの脳神経科医オリヴァー・サックスの『音楽嗜好症(ミュージコフィリア)』(ハヤカワ・ノン・フィクション文庫)を読み終えたばかりだったこともあり、快く引き受けました。
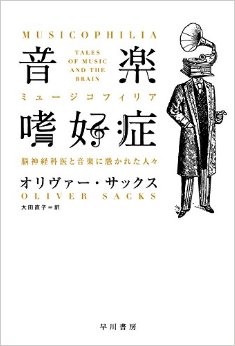
オリヴァー・サックス『音楽嗜好症(ミュージコフィリア)』ハヤカワ・ノン・フィクション文庫
数日後、編集部からサンプルDVDが届けられました。〆切が迫っているのでさっそく観ようと思ったところ、「どうせならスタッフにも観てもらおう」と緊急に施設で上映会を開くことにしました。
急な呼びかけだったにもかかわらず、上映会には入所・通所担当の介護スタッフはじめ、相談員、ケアマネージャーなど、15人ほどが集まりました。
マイケル・ロサト=ベネット監督によるこのドキュメンタリー映画は、ダン・コーエンという以前IT関連の仕事をしていたソーシャル・ワーカーが、認知症、多発性硬化症、双極性障害といった疾患により病院、介護施設、あるいは在宅で療養している人びとを訪ね、それぞれの思い出の音楽(パーソナル・ソング)を探り当てて、かれらの閉ざされた心に光を灯していく物語です。
映画の冒頭、こんな印象的なシーンがあります。
介護施設に入所して10年になる94歳の黒人男性ヘンリーは重い認知症。1日中、車イスで一人ポツンと無表情にうつむいたまま過ごしています。面会に訪れた娘の名まえさえ覚えていません。
ダン・コーエンは、ヘンリーが若い頃、熱心に教会へ通っていたという話を聞いて、彼にヘッドフォンでゴスペルの名曲’Goin’ Up Yonder’ を聞かせます。
すると、ヘンリーは突然目を輝かせ、身体を揺らしながら歌い出します。そして、若い頃の記憶や思考や気分などが次々とよみがえってきて、かれは生き生きとした表情で語り始めます。
ちなみに、ヘンリーのお気に入りは、30〜40年代に大人気だった「ミニー・ザ・ムーチャー (Minnie The Moocher) 」で知られる〝ジャイヴの王様〟キャブ・キャロウェイでした。
私もキャブ・キャロウェイは大好きです。
映画ではキャブが自らのビッグバンド率いてハイテンションで歌い踊るシーンがはさまれ、興奮した口調でキャブのことを語るヘンリーのうれしそうな表情との相乗効果によって、つい表情が緩んでしまいました。

キャブ・キャロウェイと彼の楽団
映画にはオリヴァー・サックス医師も出ています。前述の『音楽嗜好症(ミュージコフィリア)』で、彼は音楽と脳の関係について次のように説明しています。
音楽の認識は、人間の脳の1個所でおこなわれるのではなく、脳の全体に散らばっているさまざまな部位のネットワークからなっています。つまり、音質、音色、音程、メロディ、和音、リズムを感じとる脳の部位がそれぞれに分かれていて、これらを頭のなかで統合して音楽として認識するというのです。
さらにこの構造的な認識に、感情的な反応が加わって、運動をもうながします。音楽は脳の広い範囲を刺激するばかりでなく、感情を呼び起こし、身体運動をもたらすというのです。ヘンリーはそのもっともわかりやすいケースといえるでしょう。
サックス医師は、映画の中で音楽は認知症によるダメージを比較的受けにくいともいっています。
これは、音楽として認識する脳の部位が各所に散っているおかげでリスクも分散されるというふうに理解すべきなのでしょうか?
脳は通常、優位な方の脳半球がもう一方の脳半球の働きを抑え込んでいます。それが、たとえば脳卒中によって優位脳半球の広い部位が損なわれたりすると、抑制されていた脳の機能が解放されることが起こるようです。
音楽が認知症に効果があるというのは、このように解放された脳の部位を刺激し活性化させるためではないかと私は考えます。
音楽療法というと、当施設でもそうですが、集団で懐かしい歌をうたったり楽器を演奏したりするのが一般的です。ダン・コーエンの音楽療法がユニークなのは、iPodを使って一人ひとりにヘッドフォンで音楽を提供している点です。
私もランニングや筋トレのときiPodをしています。これによってざわついた外の環境からある程度、情報遮断ができ、運動に集中できるだけでなく内省が高まってイマジネーションがわいてきます。ダンがやったのはこれとおなじ原理かと思います。
(続く)
2014.12.18 |  音楽とアート
音楽とアート
小牧小5年生施設訪問〜ハイパー劇『桃太郎と桃次郎』にブッ飛びました

リコーダーの演奏を披露してくれたクラス
小牧小学校は、小牧の市街地で明治6年(1873)に開校、昨年、創立140年を迎えた伝統校。じつは私も卒業生です。
8、9年ぐらい前から、総合学習の一環として小牧小の生徒さんたちが豊寿苑を訪問してくれるようになりました。
今年は10月22日と24日の2回、5年生が2クラスごとに約70名ずつ来てくれました。
まず、生徒たちがクラスごとに話し合って決めた歌や演奏、ダンスといった出し物を披露します。
そのあと、生徒たちを囲むようにU字型に並んだお年寄りたちのところに行って、一人ひとりと対面でふれあいます。
滞在時間は1時間程度ですが、世代も生活歴もまったくちがう、かれらにとっては「エイリアン」といっていいようなお年寄りたちとの対面的なコミュニケーションが、家庭や学校とは別の社会との係わりの第一歩につながればいいと感じています。

楽しくにぎやかにダンスを披露してくれたクラス
また、お年寄りの心からの「ありがとう」の言葉を受けとめ、社会のなかで自分がひとの役に立っていることに気づいてくれたのなら、これ以上の喜びはありません。
別れ際に、感激のあまり涙を流している生徒たちやお年寄りたちを見ると、「いいことをしてよかった」という気分にさせられます。
今年もどのクラスも元気いっぱいで、それぞれに個性があってお年寄りのみなさんはとても喜んでおられました。
そのなかで、あるクラスがたいへん興味深い劇を見せてくれましたので、そのことについてくわしく書かせてもらいます。

最後はお年寄りたちとふれあいタイム
演題は『桃太郎と桃次郎』。
生徒たちのオリジナルで、いうまでもなく、昔話『桃太郎』のパロディ。話の流れは『桃太郎』のまんまなので、ここではポイントのみ記します。
桃太郎と桃次郎が鬼ヶ島へ向かう途次、イヌ、サル、キジのほか、スギちゃん、小島よしお、ふなっしーといった芸人やキャラと出会って次々とお供に加わっていきます。
こうして鬼ヶ島に着いたときには桃太郎一行は大所帯にふくれ上がっていました。その数に圧倒された鬼たちはのっけから戦意喪失。善良で気弱でマイノリティーという鬼のほうにシンパシーを感じてしまったのは、たぶん私だけではないでしょう。
そのあと、経緯は忘れましたが、お互いにあまり戦意が感じられない桃太郎たちと鬼たちとのあいだで牧歌的/遊戯的なバトルがくり広げられます。こうして収拾がつかなくなったかれらの前に、水戸黄門一行が現れて事態を丸く収めてメデタシ、メデタシ。
あとで先生にうかがったら、この話はこの夏の野外合宿のときにみんなで考えたとのことでした。

オリジナル劇『桃太郎と桃次郎』の主役の二人
私は、これは生徒たちの集合的無意識が反映されたクラスの物語だと思いました。その理由はいくつかあげられます。
まず、主役が桃太郎と桃次郎の二人ですが、これは一人だけがクラスで目立ってしまうことへの自己防衛のあらわれのようにも解釈できます。昭和36年(1961)生まれの私の時代だったら、いい意味で目立つことについてはクラスから容認され、尊敬もされていたのと隔世の感を禁じえません。
同じように、作者が生徒の一人ではなくみんなの共同脚本であるところもそうしたあらわれでしょう。
また、鬼ヶ島へ鬼退治に出かける桃太郎一行には「正義」の正当性の根拠(正当性があってこその正義なのに)が見当たりません。つまり「正しさ」の拠り所が内在的な倫理基準にではなく、最大多数の同調にあるあたりがいかにも現代的です。
だから、別に知らなくてもどうってことない、ダンディ坂野や小島よしおといった一発屋のネタを知っていることが仲間への参加要件になるのです。
鬼は悪事をはたらいたから成敗されるというより、バラバラで個性的なキャラクターの集まりである桃太郎一行が仲間としてまとまるための口実でしかないような気がします。あえていうなら、鬼であること、仲間に同調できないマイノリティーであることが退治される理由なのです。
桃太郎一行と鬼たちとのあいだには善と悪という二元論的な対立はありません。両者は見た目も性格もまったく同じで入れ替え可能です。差異がないから雌雄を決する戦いにはなりえず、中味がなく、とりとめもないやりとりがネバーエンドでくり広げられるのです。
脈絡なく降臨してくる水戸黄門は、このゲームを強制終了させるための手段です。第三項としての水戸黄門は、いうまでもなく担任の先生のメタファーです。葵の御紋という圧倒的な力を借りるほかに事態の収拾が図れないということなんでしょう。
先生の調停によってざわざわしていたクラスは一つにまとまるというハッピーエンド。しかし、この平和は長く続かないだろうことは東西冷戦終結後の世界を見てきた私たちはもちろん、当の生徒たちもなんとなくわかっているはずです。
まったく、子どもたちの創造力にはブッ飛びました。子どもはまさしく社会の鏡ですね。
2014.12.03 | 地域交流




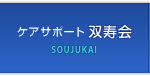


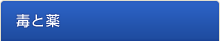
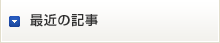
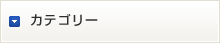
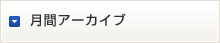
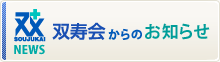
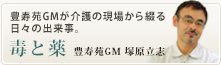
![塚原外科・内科[TEL:0568-77-3175/FAX:0568-76-8173]](http://www.soujukai.or.jp/wp-content/themes/soujukai/images/common/banner_info_tuka.png)
![老人保健施設 豊寿苑[TEL:0568-71-8281/FAX:0568-76-1498]](http://www.soujukai.or.jp/wp-content/themes/soujukai/images/common/banner_info_hou.png)
![居宅介護支援事業所 ケアサポート 双寿会[TEL:0568-73-6543/FAX:0568-73-6554]](http://www.soujukai.or.jp/wp-content/themes/soujukai/images/common/banner_info_sou.png)